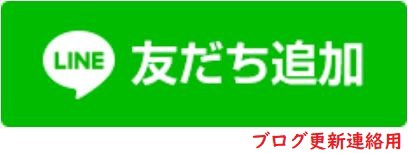スク玉ブログ
「名大生が教えても伸びない理由」我が子の学力を受験レベルまで引き上げるために必要なこと!
「内臓脂肪を減らす!」ってお茶を飲んでも痩せない さんなん です。
おかしいなって思って、冷静に考えてみました。うん、間違いない。過剰摂取、そう。食べ過ぎだわ!
さて、本日は高校生についてです。受験生という意味では、中学受験、高校受験も共通する話題です。宜しければお付き合いください。
タイトル:大学受験において、最後の最後まで学力を伸ばす!ために。
そもそも「成績を伸ばすという工程」のはシンプルです。
➀「理解する」段階(インプット)
②「できるようになるまで練習する」段階(アウトプット)
多くの教材や授業が重視しているのは➀です。学校の授業や映像教材、参考書や個別指導も「わかりやすく説明する」ことに力を注いでいます。
生徒は「理解したつもり」にはなるのですが、それだけでは成績アップはしません。おかしいですよね。
本当に成績を伸ばすために、抜け落ちている考え方は、②の「練習」です。ここをどこまで徹底できるかどうかで差がつきます。
小中学生のご家庭で、お父さんが「ここはこう解くんだよ」と説明しても、なかなか結果につながらないのは、この②の部分が抜け落ちやすいからなんですよ。
理解で終わってしまい、「できるまでやり込む」段階に届かないのです。でもこの②の部分って、相当考え方は難しいのです。
名古屋大学の学生を例にとるとわかりやすいでしょう。
名大生は、自分の勉強法にゆるぎない自信を持っています。実際に、質の高い勉強を継続して成果を出してきたからです。だからこそ、➀の「理解する力」には長けています。
ただし、「説明がわかりやすいかどうか」はまた別問題。そして②の「練習を支える力」となると、さらに別物です。
名大生本人にとっては「できるまでやる」「調べるまでやめない」「長時間勉強する」のが当たり前。中には「一度解けば理解できる」というタイプもいます。
でも、それは多くの生徒にとって決して当たり前ではありません。
本当に必要なのは、その子の学力と志望校に合わせて、「どんな練習を、どれくらいの量で、どの順序でやるのか」を優先順位をつけて設計してあげること。
これこそ塾の役割であり、経験も実践も積んできたスク玉の強みだと考えています。
大学受験は科目数も多く、課題も膨大です。与え過ぎればオーバーワークになるし、間違い直しや理解度にも個人差があります。
だからこそ、一人ひとりに合った学習ペースを見極め、計画を丁寧に立てていく必要があります。
学校は集団授業なので、小論文対策のような分野でさえ、一人ひとりに寄り添うことは難しい(これは最近増えてきたご相談ですね。一人、1週間に1つまで)。
「巷で流行っている『この大学に行くならこの教材』というルートも、結局は➀の部分に偏っており、伸び悩むのも無理はありません。
保護者が大量に問題集を買い与えても、上手くいかないケースもこれと同じですね。
高校生にもなると個人の学力差が開き、一人の成功体験をそのまま他の子に再現するのは難しいです。
現役生の受験は、受験の直前、「最後の最後まで伸びるかどうか」で勝負が決まります。塾では10月から本格的に実践形式に入りますが、その成果が出るのは早くても12月以降です。
1週間単位でやることを決め、個別に理解度を確認。すぐに得点を求めるのではなく、改善ポイントを一緒に探っていく。こちらも焦る気持ちを抑え、我慢、我慢の連続です。
これも過去の多くの経験値があるからこそできることで、生徒の伸びをしっかり支え、本人の力を最大限に引き出すことができるのも、私たちのような塾の存在だと思っています。
やっぱり受験の本番を乗り越えるには、「学校だけに任せる・自己流や家庭学習だけ」では限界があります。
だからこそ、今このタイミングで塾にお任せいただけたらと思っています。
(LINE@登録でお問合せ【お問合せ専用】)
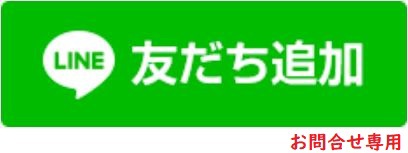
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
スク玉ブログ連絡用LINE@を作りました。よかったらご登録ください。(塾生の方も、塾生でない方もどうぞ)
※塾連絡は、塾生専用のLINE@にてご連絡します。
↓↓↓このLINE@の用途は、スク玉ブログの更新のみ↓↓↓
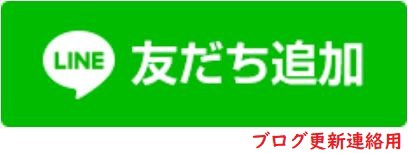
おかしいなって思って、冷静に考えてみました。うん、間違いない。過剰摂取、そう。食べ過ぎだわ!
さて、本日は高校生についてです。受験生という意味では、中学受験、高校受験も共通する話題です。宜しければお付き合いください。
タイトル:大学受験において、最後の最後まで学力を伸ばす!ために。
そもそも「成績を伸ばすという工程」のはシンプルです。
➀「理解する」段階(インプット)
②「できるようになるまで練習する」段階(アウトプット)
多くの教材や授業が重視しているのは➀です。学校の授業や映像教材、参考書や個別指導も「わかりやすく説明する」ことに力を注いでいます。
生徒は「理解したつもり」にはなるのですが、それだけでは成績アップはしません。おかしいですよね。
本当に成績を伸ばすために、抜け落ちている考え方は、②の「練習」です。ここをどこまで徹底できるかどうかで差がつきます。
小中学生のご家庭で、お父さんが「ここはこう解くんだよ」と説明しても、なかなか結果につながらないのは、この②の部分が抜け落ちやすいからなんですよ。
理解で終わってしまい、「できるまでやり込む」段階に届かないのです。でもこの②の部分って、相当考え方は難しいのです。
名古屋大学の学生を例にとるとわかりやすいでしょう。
名大生は、自分の勉強法にゆるぎない自信を持っています。実際に、質の高い勉強を継続して成果を出してきたからです。だからこそ、➀の「理解する力」には長けています。
ただし、「説明がわかりやすいかどうか」はまた別問題。そして②の「練習を支える力」となると、さらに別物です。
名大生本人にとっては「できるまでやる」「調べるまでやめない」「長時間勉強する」のが当たり前。中には「一度解けば理解できる」というタイプもいます。
でも、それは多くの生徒にとって決して当たり前ではありません。
本当に必要なのは、その子の学力と志望校に合わせて、「どんな練習を、どれくらいの量で、どの順序でやるのか」を優先順位をつけて設計してあげること。
これこそ塾の役割であり、経験も実践も積んできたスク玉の強みだと考えています。
大学受験は科目数も多く、課題も膨大です。与え過ぎればオーバーワークになるし、間違い直しや理解度にも個人差があります。
だからこそ、一人ひとりに合った学習ペースを見極め、計画を丁寧に立てていく必要があります。
学校は集団授業なので、小論文対策のような分野でさえ、一人ひとりに寄り添うことは難しい(これは最近増えてきたご相談ですね。一人、1週間に1つまで)。
「巷で流行っている『この大学に行くならこの教材』というルートも、結局は➀の部分に偏っており、伸び悩むのも無理はありません。
保護者が大量に問題集を買い与えても、上手くいかないケースもこれと同じですね。
高校生にもなると個人の学力差が開き、一人の成功体験をそのまま他の子に再現するのは難しいです。
現役生の受験は、受験の直前、「最後の最後まで伸びるかどうか」で勝負が決まります。塾では10月から本格的に実践形式に入りますが、その成果が出るのは早くても12月以降です。
1週間単位でやることを決め、個別に理解度を確認。すぐに得点を求めるのではなく、改善ポイントを一緒に探っていく。こちらも焦る気持ちを抑え、我慢、我慢の連続です。
これも過去の多くの経験値があるからこそできることで、生徒の伸びをしっかり支え、本人の力を最大限に引き出すことができるのも、私たちのような塾の存在だと思っています。
やっぱり受験の本番を乗り越えるには、「学校だけに任せる・自己流や家庭学習だけ」では限界があります。
だからこそ、今このタイミングで塾にお任せいただけたらと思っています。
(LINE@登録でお問合せ【お問合せ専用】)
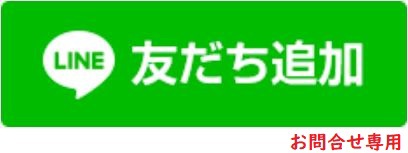
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
スク玉ブログ連絡用LINE@を作りました。よかったらご登録ください。(塾生の方も、塾生でない方もどうぞ)
※塾連絡は、塾生専用のLINE@にてご連絡します。
↓↓↓このLINE@の用途は、スク玉ブログの更新のみ↓↓↓